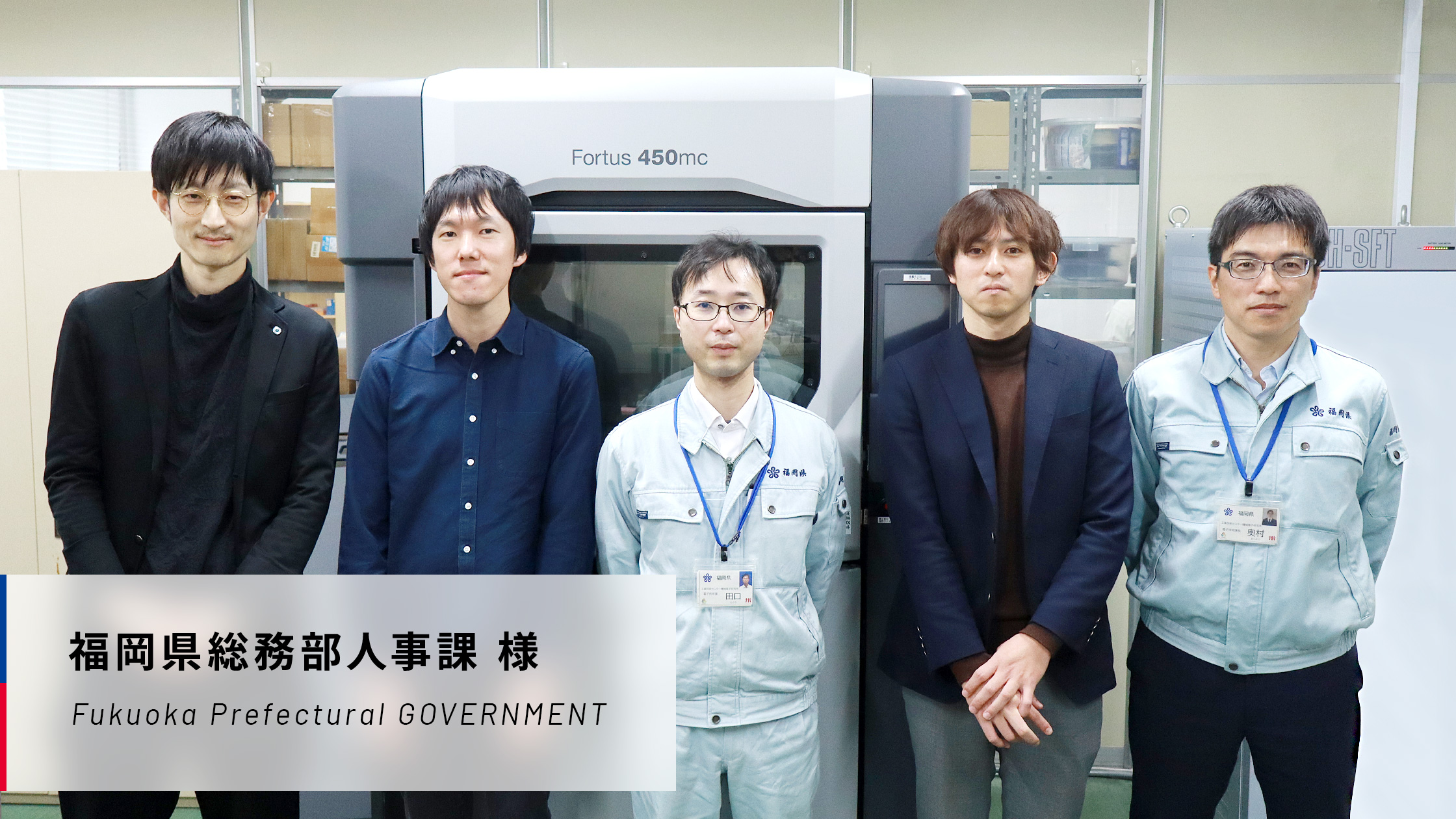2023年に福岡県総務部人事課様は、Fusicが開発したQRコード勤怠管理システムを本庁に導入しましたが、その成功を受けて、次は100箇所を超える出先機関への展開を検討されていました。そこでFusicは、出先機関での利用に適したQRコードリーダーIoTデバイスを新たに考案。福岡県工業技術センター 機械電子研究所様の参加も決まり、プロジェクトが始動しました。
▼今回の開発事例
QRコードで打刻するIoTデバイスを考案、勤怠管理システムの水平展開を実現
インタビュイー:
福岡県総務部人事課 松田 啓佑 様
機械電子研究所 田口 智之 様
前プロジェクトから間髪入れずに新規プロジェクト開始
Fusic 賀来)2023年11月に福岡県の本庁でQRコードによる勤怠打刻システムの本格運用が始まりましたが、その後間髪入れず3月に「県内外に100数箇所ある出先機関にも拡張したい。」と松田様からお話をいただきました。本庁のプロジェクトが始まる当初からその構想は伺っていたものの、福岡県庁という大きな組織でこのスピード感には驚かされました。
福岡県 松田 様)ありがとうございます。出先機関には、お店や空港などに置いてあるようなQRコードを読み取る専用のデバイスを作って展開したいとお伝えしました。
Fusic 岡嵜)私はその話を聞いてすぐにデバイスの試作を開始しました。松田さんのご要望にうまく合いそうなQRコードリーダーモジュールとマイコンボードを使って今回のデバイスのコアな部分はすぐにできました。
福岡県 松田 様)あとは、そのデバイスの量産体制をどうするかという課題が残っていたのですが、県庁内を当たっていたときに、この手のデバイスを扱ったことがあるという福岡県工業技術センター 機械電子研究所の存在を知りました。コンタクトして相談してみたところ、幸運にも参画いただけるというお返事をいただきました。こうして総務部の人事課、商工部の機械電子研究所、Fusicの三者協力体制が整い、プロジェクトをスタートすることができたんです。
IoTデバイスの改良プロセス
Fusic 岡嵜)私が作ったデバイスの初号機から、筐体は3Dプリンターで作っており、通信にはもちろんSORACOMを採用しています。県庁様とのプロジェクトとは別に、個人的にSORACOM DiscoveryというIoTのイベントでこのデバイスを展示する予定もあったので、それも見据えつつまずは私の手元で改良を重ねていました。
機械電子研究所 田口 様)プロジェクトが本格始動してからは、私たち機械電子研究所が、岡嵜さんの作った基本構成やソフトウェアを引き継いで、より実運用に即したものを目指して改良を重ねました。機械電子研究所の中で、機械系に強い人、ソフトウェアに詳しい人、電子回路が得意な人など、それぞれの専門分野を持つメンバーが役割分担して進めることで、スムーズに開発が進みました。
機械電子研究所 田口 様)USBケーブルの固定方法や筐体形状の変更、全体のコンパクト化など、細かな点も一つひとつ改善を重ねていきましたね。
福岡県 松田 様)視覚障がいや聴覚障がいのある方に配慮した仕様もありがたかったです。
機械電子研究所 田口 様)元々音は鳴るように作られていたのですが、LEDを追加することで聴覚障がいの方には光でスキャン結果をお知らせするように改良しました。結果的に、この機能は聴覚障がいのない方にもわかりやすくなって好評と聞いています。
福岡県 松田 様)はい。最終的には非常にシンプル且つ理想的な形にまとまって「これが正解だったな」と思えるような仕上がりになりました。本当に完璧です。
機械電子研究所 田口 様)次は量産という壁があり、これにもさまざまな工夫が必要でした。機械電子研究所では試作で1〜2台作ることはあっても、これほどの量を製造するという前例はなかったのです。通常業務とは違う特殊なミッションだったのですが、機械電子研究所にはものづくりが好きなメンバーが集まっているので、忙しさはさておき、みんなが興味を持って取り組めたのではないかと思います。 通常業務と並行して進めるため、業務に支障が出ないように工程表を作成し、各自の業務と調整しながら進めていく形を取りました。こうしたスケジュール管理がうまくいったことで、プロジェクトが円滑に進んだと思います。
Fusic 岡嵜)これはすごい。しっかりしたマニュアルですね。私たちには見えていなかったところで、こんなに多くの方々が協力してくれていたとは知りませんでした。
クラウドアプリケーションについて
Fusic 賀来)クラウドアプリケーションに関しては、元々作っていたシステムに対して今回のデバイス用にデータの入口部分を追加したり、松田様からご依頼いただいた改修をいくつか実装しましたが、当然ながらシステムのベース部分は2023年に構築したものをそのまま活用しています。 サーバーレスというアーキテクチャを採用しているため無駄な費用がかからない設計になっています。従来のように常時サーバーを立てておく必要はなく、使った分だけAWSのリソースを使うので非常に効率的です。
Fusic 岡嵜)通信に関してですが、本庁同様、出先機関も全箇所セルラー通信で対応する必要がありました。FusicはIoTプラットフォーマーであるソラコム社のパートナーなので(※)導入は非常にスムーズでした。出先機関100数箇所の中には山間部の事務所など特定のキャリアの電波が届かない箇所もありましたが、ソラコム社からのサポートもあり最終的には全箇所安定した通信を実現しています。
※FusicはSORACOMパートナースペース(SPS)における 上位認定資格「SELECTEDインテグレーションパートナー」 です。
詳しくはこちら
システム導入
福岡県 松田 様)新しいシステムの導入には、ユーザーである職員にきちんと説明して納得してもらうことが大切だと考えています。今回も各出先機関に対して説明会を開催したり、問い合わせにきめ細やかに対応することを心がけました。 正直なところ、人事課として普段は本庁内での業務が中心で、各出先機関と深く関わることはあまり多くはありません。今回の導入を通じて、多くの出先機関と密にやりとりすることとなり、各職場の業務や環境について理解を深めることができたのは、私自身とても良い経験になりました。
今までは残業や出退勤の実態が把握しづらいという課題がありました。今回のシステム導入によって、職員ごとの勤務状況が可視化されたことで、所属長が適切な業務分散を行い、「本当にこの業務が必要なのか?」といった判断ができるようになったのは大きなメリットです。本庁のプロジェクトを始動した当初は他の勤怠管理システムも検討していましたが、出先機関を含めて導入だけで数億円かかるというものもあり、コストが大きなネックになっていました。それがFusicさんのご提案だと、驚くほどの低コストで導入でき、かつランニングコストもしっかり抑えられて本当に良かったです。
今回は民間企業に全面的に委託するのではなく、機械電子研究所が参加してくれたことも大きな意味がありました。というのも「部門間の壁をなくして横断的に連携する」というのが、福岡県としての大きな方針になっているからです。今回のプロジェクトは、まさにそれを体現する成功例となりました。
Fusic 賀来)私の狭い観測範囲内では、出先機関まで含めて専用デバイスを配置して勤怠打刻している自治体は今のところ福岡県だけです。この事例が刺激となって他の自治体にも横展開されて、日本全体のDXが進んだらいいなという夢を描いています。
福岡県 松田様)実際、前回の事例を見た全国の自治体から私の元に問い合わせが続々と来ています。その際「Fusicさんと相談してシステムを作り上げました」とお伝えしています。Fusicさんや機械電子研究所には多くの要望を出してきましたが、その都度、丁寧に対応していただき、本当に助けられました。