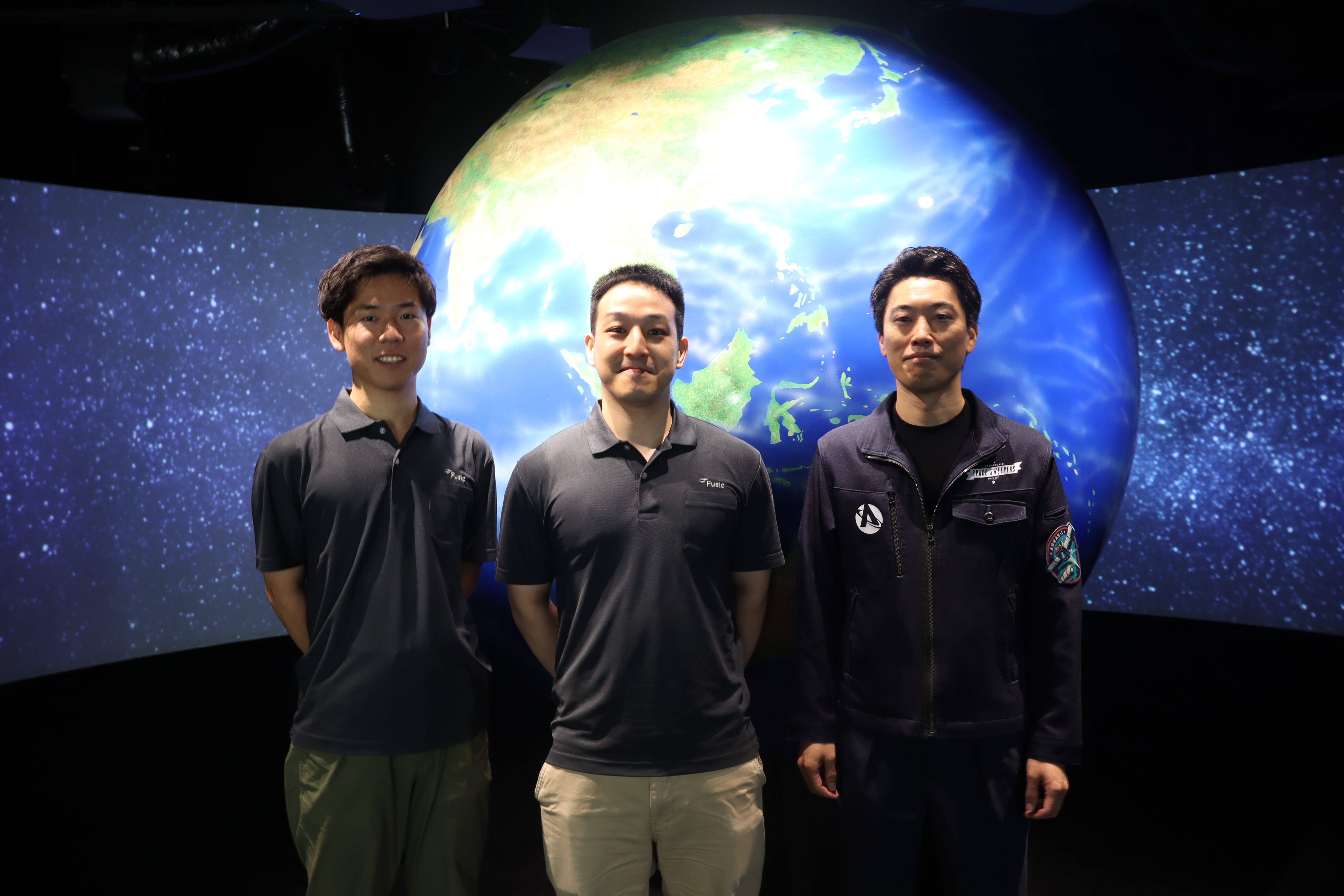インタビュイー
- 株式会社アストロスケール 八木様
- Fusic 槇原
インタビュアー
- Fusic 吉野
インタビューサポート
- Fusic 室井
宇宙ゴミ(デブリ)除去や人工衛星の寿命延長などの軌道上サービスを提供する、日本の宇宙スタートアップ企業・株式会社アストロスケール様。同社は、宇宙産業において革新的な技術開発を進める一方で、「クラウドインフラの整備」という重要な課題にも直面していました。
今回、当社がAWS基盤の構築支援を通じて、アストロスケール様の事業を技術面からサポートさせていただいたプロジェクトについて、詳しくお話を伺いました。
▼Fusicとアストロスケール、コーポレートパートナーシップを締結
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000046080.html
宇宙事業におけるITの重要性
宇宙事業とソフトウェアの密接な関係
インタビュアー:
御社の事業におけるITインフラの重要性について、教えていただけますか?
アストロスケール様:
人工衛星は設計、解析、管制も含め、ハードウェアとソフトウェアの融合であり、ソフトウェアなしでは成立しません。
当社が軌道上サービスを提供する上で、ITインフラの安定性は極めて重要です。ITインフラにトラブルがあれば開発が遅れてしまうため、強固なIT基盤を構築し、軌道上サービスのアプリケーションが稼働しても安定した環境を維持することが不可欠です。
クラウド活用の理由
インタビュアー:
クラウドは、御社の事業においてどのような役割を担っていますか?
アストロスケール様:
クラウドの最大の利点は、リソースを柔軟に割り当てられる点です。日々変化する計画に対して迅速に対応できることから、積極的に活用しています。
機器を購入・設計するための時間もリソースも限られているため、オンプレミス(※)より簡単に利用できるクラウドは、スタートアップ企業である当社にとって非常に相性が良いと言えます。現在はハイブリッド構成を採用しており、柔軟性が求められる部分はクラウドなど、適材適所で使い分けています。
※オンプレミス:サーバーやソフトウェアなどのシステム基盤を、企業が自社の施設内に設置し、自社で保有・運用する形態。最大容量の面で柔軟なクラウドと違って制限があるため、用途に応じて使い分ける傾向にある。
宇宙産業でのクラウドの成長と可能性
インタビュアー:
宇宙産業でクラウドが使われる理由は、何でしょうか?
アストロスケール様:
リソースが限られている中で、すぐに環境を作り、試してみるといった開発サイクルを実現できる点で、クラウド導入のニーズがあります。オンプレミスで運用している企業はほとんどなく、今後新たに参入する企業もクラウドを選択するでしょう。
Fusic:
宇宙産業の市場が拡大している今だからこそ、早い段階からアプローチし、最初からクラウドネイティブ(※)でサポートできる可能性があると考えています。
※クラウドネイティブ:最初からクラウド環境でアプリケーションを実行したり、ソフトウェアを開発したりすることを前提とした考え方。
株式会社アストロスケール 八木様
Fusicとのパートナーシップ
決め手となったのは柔軟な対応力
インタビュアー:
様々なクラウドサービス会社がある中で、当社を選んでいただいた決め手を教えていただけますか?
アストロスケール様:
きっかけは、クラウドの脆弱性診断でした。当社にはその対応リソースがなかったためサポートをお願いし、そのご縁からクラウド構築の支援も依頼するようになりました。
いつも真摯に相談に乗っていただき、「一緒に仕事をしている」という強い実感があります。担当者の方が同世代ということもあり、コミュニケーションが取りやすい環境です。
さらに、当社の要求に対してプラスαの提案をいただくことも多く、選択の幅が広がるのは非常にありがたいです。
支援内容について
インタビュアー:
具体的には、どのような支援をさせていただいたのでしょうか?
アストロスケール様:
AWS基盤の構築を支援していただきました。これまではクラウドリフト(※)を利用していましたが、マネージドサービス(※)を活用し、クラウドをより有効に使える環境を整えたいと考え、サポートをお願いしました。
※クラウドリフト:既存のオンプレミス環境にあるシステムやアプリケーションを、最小限の改修でそのままクラウド環境へ移行する手法。
※マネージドサービス:企業の情報システムに必要なインフラ(サーバーやネットワークなど)の運用・管理・保守を、AWSが定義するオペレーションベストプラクティスのガイダンスに基づき、自動的に実行できるサービス。
約1年前から設計を始め、要件定義→基本設計→詳細設計の順で進め、構築段階では技術的なサポートをいただきました。社内に知見が少なかったため、多くの情報を提供いただき、選択肢が増えたのはとても大きな成果でした。
技術的な工夫と課題解決
要件定義からの徹底したアプローチ
Fusic:
今回のプロジェクトでは、スタート時点から要件定義をしっかり行うことを重視し、AWSが推奨する「AWS Well-Architected Framework(※)」に基づいた構築を、最初にご提案しました。アーキテクチャ(論理構造)の各ポリシーに対して、「これは実現可能」「これは現実的に難しい」といった検討を一つひとつ丁寧に行い、できる限りフレームワークに近づける形で進めました。そしてコスト面やシステム特性を踏まえながら、バランスの取れた仕様を決定しました。
※AWS Well-Architected Framework(AWS ウェルアーキテクテッド フレームワーク):AWSクラウドでシステムを設計・運用する際のベストプラクティスをまとめたガイドライン。
アストロスケール様:
「AWS Well-Architected Framework」を活用する提案をいただいたのは、大きなポイントでした。当初は自分たちの要件をどう実現するかという視点で考えていましたが、「こういうアーキテクチャで網羅されているので確認してみましょう」と提案いただき、バランスを取りながら相談に乗っていただけたのがとても良かったです。
伴走型サポートの効果
インタビュアー:
構築段階では、どのような形でサポートさせていただいたのでしょうか?
Fusic:
定例会議で「こういう課題があるのだが、どう対応すれば良いか?」といった相談を受けたり、質問表を用意してやり取りしながら、定期的にまとめて報告する形で進めました。技術検証も並行して行い、実際に手を動かして確認していただくことを重視しました。
アストロスケール様:
AWSの知見を持つ方から直接アドバイスをいただけたのは、非常に助かりました。やりたいことは頭にあっても、それをAWS上でどう実装するか迷うような場面で、実際に手を動かして確認してもらえることが大きな支えになりました。
クラウド活用の課題と解決策
選択肢の多さという課題
インタビュアー:
クラウドを使う上で難しいと感じるところはありますか?
アストロスケール様:
クラウドは便利に利用できますが、選択肢が多すぎて分かりにくいというのが最大の課題です。「どの設定が最適なのか」という経験を積まないと分からない部分は、専門家の存在が必要だと感じています。
例えば、Aurora Serverless(※)の設定が適切でなかったためにデータベースに意図しないコストが発生していたり、セキュリティ設定に漏れがあったりと様々な課題がありましたが、Fusicさんとのやり取りを通じて一つひとつクリアしていきました。
※Aurora Serverless:AWSが提供するサーバーレス型のデータベースサービス。
技術者育成の課題
インタビュアー:
他にもシステム開発において課題があれば、教えてください。
アストロスケール様:
専門性の高い人材がそれぞれのサブシステムを担当する中で、「AWS全体を誰がコーディネートするのか」という課題があり、ソフトウェア開発を体系化する技術者育成を急いでいます。
当社の創業者の言葉を借りれば、人工衛星や軌道上サービスは「総合格闘技」です。様々なシステムがあり、多くのエンジニアがグループやチームで関わっていますが、統合管理や統制は複雑化しています。今後はソフトウェアも含め、体系的に管理できる仕組みを確立していく必要があると考えています。
今後の展望
マネージドサービスの活用拡大
アストロスケール様:
今後、当社が打ち上げる人工衛星の数はさらに増える見込みであり、マネージドサービスをより活用し、ゼロからのITインフラ構築を減らすことで、そこに人手をかけずに進められる体制を目指しています。
また、生成AIについても社内エンジニアから利用の要望が出ており、データの扱いを検討しながら段階的に導入を進めていく予定です。
クラウド活用の重要性は、一層高まっていくと思いますね。
宇宙産業企業へのアドバイス
インタビュアー:
最後に、クラウド導入を検討している宇宙産業の企業へアドバイスがあればお願いします。
アストロスケール様:
クラウドには多くのメリットがありますが、その利点が自社に本当に適しているのか、導入すべきかを慎重に検討することが重要です。
また、適切に活用しなければ期待した効果を得られない場合もあるため、Fusicさんのように知見を持つ専門家に相談しながら進めるのが最善だと考えています。
まとめ
今回のプロジェクトを通じて、宇宙産業におけるクラウド活用の可能性と課題が見えてきました。技術的な知見だけでなく、パートナーシップの重要性や継続的なサポートの価値を改めて実感します。
【クラウド活用の可能性】
- 必要な時にすぐ環境を作れるため、開発や実証のスピードが上がる
- オンプレミス環境を自前で用意しなくてもよく、コストや手間を減らせる
- 人工衛星の数が増えても対応できる柔軟な仕組みをつくれる
【クラウド活用の課題】
- サービスや設定が多すぎて、適切な使い方を選ぶのが難しい
- セキュリティやコストの管理を誤ると大きなリスクになる
- 全体をまとめて管理できる専門人材が不足している
宇宙産業はソフトウェアとクラウド技術が成功の鍵を握っています。宇宙産業全般でIT人材が不足している現状において、信頼できる技術パートナーとの協業は不可欠です。
Fusicでは、宇宙産業をはじめ多様な業界のお客様に対し、単なる技術提供に留まらず、伴走するパートナーとしてビジネスの成長を支援しています。今後も革新的な技術とサービスを通じて、お客様の事業発展に貢献してまいります。